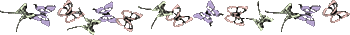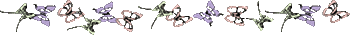
木下あゆ美のメジャーデビュー作「正義は勝つのよ。結果はどうあれ、私はそう信じたい」
人物の個性を表現するよりもその立場を説明するだけで成り立つ物語は多い。その方が見る側もわかりやすいし、作る側にとって作りやすいからである。演技力が不足していても成立するので、深みも濃くもない話になってしまいがちであるから、演技力のある役者からすればこれほどつまらない芝居もない。立場だけで成立する芝居というのは、幼稚園の発表会で演じられるお芝居の役と同じである。テレビドラマの場合はキャスティングの段階で無難な配役をしてしまうので、役者は「いつもの役」を繰り返していればよかったりする。サスペンスドラマの刑事がいつもトレンチコートをきているようなものだ。テレビ作品という即物的な商品にとって実験は歓迎されない。そのような制作環境では役者の新境地はありえない。とはいえ、テレビドラマ制作はファーストフード的であるし、そのような軽いドラマが求められてもいる。また視聴者も歯が弱ったのか堅いドラマは避けるし、胃も丈夫ではないのか重いドラマは受け付けない。需要と供給のバランスが均衡しているのが昨今のテレビドラマと視聴者の慣例ではなかろうか。
映画の黄金時代、映画は文化の伝搬を一手に引き受けていた。足袋裸足の子供たちに摩天楼を夢見させてくれるのは映画でしかなかった。焼け跡の疲弊した人々に夢を与えたのも映画だった。やがてテレビが普及し、夢が買えるようになり、その夢を売る自動販売機がお茶の間にやってきた。昭和四十年代、まだまだテレビは「物」に象徴される夢のある生活をアピールし続けていた。しかし、「物」が満ち足りた平成の世の中では「物」には夢が宿らなくなった。人々にとっては欲しいものは既に「必要な物」ではなくなっている。物を作り、売る立場の側からすればテレビは必要でないものを「必要な物」と思いこませるための洗脳装置になってしまった。必要でない物を欲しがって、ローンに追われ自分の体や時間を切り売りして働いている人々もいる。必要でない「必要な物」のために体や時間を失っている。失った体や時間は取り戻せないのに、そこに自分の幸せがあると思いこんで夢中になっている。過去への夢物語であるテレビ時代劇が衰退し、未来への夢物語であるテレビSFがお子様やオタク様向けの域を抜け出せないのは、一般の視聴者がドラマに夢を託していないからだろう。夢が「物」に宿るという幻想を視聴者に繰り返し説き続けているのは、テレビCMやテレビショッピングだけなのかもしれない。
テレビプログラムの中でドラマとCMが一体となって夢を売るジャンルがある。それが子供向け番組である。ただのスナック菓子を爆発的なヒット商品に変身させた「魔法の厚紙」ライダーカードの魔力を引き合いに出すまでもなく、子供とテレビのキャラクターとの蜜月は続いている。大人よりも確実に子供の方が夢を持っていることに異論を挟む者はいまい。その子供向け番組の中でも徹底的に低年齢層向けに作られている特撮番組がスーパー戦隊シリーズだ。各話のクライマックスに必ず巨大ロボットが登場するのは、それが最大の商品になるのだから当然である。放送が終わるといくら値引きしても相手にされない際物玩具が、テレビ放送中はバンバン売れる。玩具店の商品入れ替え時期に呼応し、1クールごとに物語に新機軸が加わる。サブキャラやサブロボが次々と投入されるのもお約束である。「仮面ライダーBLACK RX」や「ウルトラマンティガ」以来、東映も円谷も露骨なほどの商魂を発揮して、主役自体がさらに変身を遂げキャラクターアイテムという商品を増やし続けている。が、戦隊物は不思議と主役キャラクター自体がさらに変身することは少ない。(注・1)低年齢層の子供を惑わさないためなのか、それとも可変合体ロボットの商品には十分な利益が見込めるので、主人公をさらに変身させる必要がないのか。主人公そのものをマイナーチェンジしていくことは、子供がやっと手に入れたヒーローの人形の価値を下げ、新商品に目移りさせる手口なので、子供心を裏切るようで許し難い。子供の購買力は無限ではないし、裕福な子供だけでないのだ。万事、細分化を好むマニア向けの商売ならば、もっと別なジャンルでやって欲しいものだ。最終クールにおいて究極の進化を遂げるのがこの手の番組のセオリーだが、クリスマスセールを見込んでのことだと思うと悲しい。しかし・・・しかし特撮には金がかかる。玩具が売れないとスポンサーは集まらず、製作費が集まらない。製作費が集まらなければよい作品は生まれない。とはいえスポンサーの売りたい商品がマニア向けのものならばどんな値段を付けようと自由だが、純粋な子供向け商品に関しては十分な配慮が必要だ。チープな厚紙にですら子供は夢を託せるのだから。
戦隊物はドラマ部分が一話当たり十三分ほどで、残り時間はヒーローが商品のプロモーションを始める。登場するキャラクターは個性ではなく役割で文字通り色分けされている。しかし戦隊ヒーローは二十八年間片時の休みもなく続いている驚異の長寿番組であるので、時には役割でなくて個性を描くことに成功する時もある。長い伝統の上に立って、見事に「役割」に「個性」を宿した傑作の一つが「特捜戦隊デカレンジャー」なのである。元々、「最後に巨大ロボットさえ出せばいいんでしょう。」というスタッフの開き直りから、かなり自由度の高い作品を生み続ける戦隊物スタッフたちである。今回は真っ向から刑事物や時代劇、昭和の笑いのエッセンス(ジャスミン担当)までぶち込み、役割や立場を極めることでベースラインを設定し、役者の個性を引き出すことに成功し、エンタメとして一級品の面白さを醸し出しつつある。

何故か探偵作家とお茶とカラーを織り込んだ命名。刑事物なので探偵作家からなのはまだ納得できる。何故お茶なのか理解に苦しむが、多分、クリスティからの連想なのではあるまいか。
登場人物名 |
変身後 |
探偵作家名 |
お茶 |
カラーとの関係(私見) |
赤座伴番 |
デカレッド |
アガサ・クリスティ |
番茶 |
赤座の赤がそのままレッド。 |
戸増宝児 |
デカブルー |
トマス・ハリス |
ほうじ茶 |
機関車トーマスのボディカラーはブルーだから。 |
江成仙一 |
デカグリーン |
エラリー・クイーン |
煎茶 |
クイーンのもじりでグリーン。 |
礼紋茉莉花 |
デカイエロー |
レイモンド・チャンドラー |
ジャスミン茶 |
レイモンがレモンだからイエロー。 |
胡堂小梅 |
デカピンク |
野村胡堂 |
梅こぶ茶 |
梅の花はピンク色だったりする。 |
レッドは名前にそのまま赤が入っている。レイモンをレモンと発音してレモンだから黄色。梅の花はピンク色である。苦しいがクイーンがグリーンなのだろう。一番、頭を悩ましたのはブルーなのだが、これは「機関車トーマス」の車体の色がブルーだからではないかと推理した。その他にネットで知った説によるとジャスミンの花は黄色、梅茶の色はピンク、煎茶は緑色、茶の焙じ方に「青焙じ」という仕方がある等々、百家争鳴である。真相は如何に。
レッド(射撃訓練の点数187/200)はお決まりのイケメンの熱血漢なのだが、ちとデッサンが狂っているように見せているところがミソである。四文字熟語を連発する口癖を持っている。二丁拳銃でジュウクンドーという「ガンカタ」を使う。ブルー(200/200)はクールでニヒルなエリートタイプ。おかしな和製英語を連発する射撃の名手。グリーン(176/200)はおっとりとした癒し系。草薙剛風の個性で、逆立ちして閃くなんてのは古谷一行の金田一耕助張りである。イエロー(171/200)はグラビア系で昭和の一発ギャグを口にし、なにげにエスパーだったりする。ピンク(67/200)はまんまハロプロ系でミニサイズ。得意技は入浴シーンだったりする。役割や立場をよくぞこてこてに設定したもので、ここまで典型的にしてあれば後は生身の役者の個性が次第に醸し出されていくのを待つばかりだ。
特撮番組は新人の登竜門である。他の色に染まっていない役者の卵たちのデビュー作である。しかも一年かけて実際にその役を演じ続けていくわけだから、次第に演技も上達し、役者の個性そのものが登場人物と同化を果たしていく。そして唯一無二の魂がキャラに宿ってくる。ストーリーも2クールから3クール目ともなると、今までに出来上がった作品からのフィードバックを得て、構想や脚本や設定が役者用に練り直されて新たに物語が紡がれていく。各話ごとに主人公を明らかに割り振って描いていくのは「太陽にほえろ!」的な展開であり、連続物の強みでもある。この手の番組から俳優として大成する者が少ないのは一年間で役者としてエネルギーを燃焼してしまうからかも知れない。人気子役が大成しない現象に近い。完全燃焼してそのままフェードアウトするか、そのまま完全に燃え続けるか。「仮面ライダーアギト ProjectG4」や「百獣戦隊ガオレンジャーVSスーパー戦隊」で藤岡弘や宮内洋が若手の激励に現れるように、未だにその初志を燃焼し続けている役者もいる。その道を極めた達人は偉大である。アニメソングの王と言えばささきいさおだが、変わらぬ歌声を本作のエンディングで披露している。
その他の登場人物、ボスであるドギー・クルーガーは名前通りの犬、の様な顔の宇宙人である。普段は司令室から動かないが、いざというときは現場に出動し、往年の藤堂俊介(「太陽にほえろ!」のボス)並みの活躍を見せる。デカマスターに変身してデカレンジャーを上回る親父パワーを炸裂させる。マスタースーツを装着すると口と足が小さくなって強化服の中に収まってしまうのが不思議だが、そこは未来の科学で操作しているのだろう。ちなみにデカマスターへの変身は1クールの終わりのイベント編だった。明らかに手抜きの命名である白鳥スワンは保健室の先生みたいな雰囲気を持つメカニックの担当者。開発からメンテナンスまで一手に引き受けている。往年のアイドル、石野真子がこの天才科学者を「九月の空」と少しも変わらぬチャーミングさで演じている。とはいえ、他のレギュラー陣がまだ生まれる前からアイドルをしていた人物なのだから、人に歴史ありである。2クールの終わりに投入された新商品、いや新キャラクターが「夜明けの刑事」ことデカブレイクである。特キョウと呼ばれる、いわば火盗改めのエリート刑事、姶良鉄幹(アイラ・レヴィン+鉄観音茶+アイボリー?)。この若手エリートがレギュラー陣と敵対するドラマが続くのかと思いきや、あっさりと後輩のポジションにおさまってしまった。主婦層に人気爆発のかわいいイケメン君である。2クールを終えて厳格な父たるボス、慈母たるスワン、弟分たるテツが出揃い、デカレンジャーはファミリー色を強めている。ちなみに世界一キャラが立っている戦隊物は黒澤明監督の「七人の侍」である。「ロード・オブ・ザ・リング」や「リーグ オブ レジェンド」も集団ヒーロー物だが、キャラクターの鮮やかさにおいては「七人の侍」を凌いだとは思えない。
敵は宇宙の個人的な犯罪者である。○○星人の○○ときちんと名前が紹介されているのも、芸が細かい。星間宇宙戦争中でもなければ国際テロ組織が相手なのでもない。侵略者を迎撃する軍隊ではなく、あくまでも犯罪者を取り締まる警察組織という世界観なのである。○○○人はすべてテロ組織とつながっているとかいうお粗末な意識はここにはない。基本的にストーリーは一話完結であり、年間を通じての敵組織が登場しないので、最終クールをどう盛り上げるのかが今後の課題である。
地球署の存続をかけて、宇宙警察全体の不正と対決する……となると「特捜戦隊」ならぬ「特捜最前線」になってしまう。低年齢層の子供にまで警察組織の腐敗とかを教えることはあるまい。最終回にボスが殉職したら「明日の刑事」になってしまうが、あれは後味の悪い最終回だったからやめてほしい。レッドが殉職したら「西部警察」かな。宇宙最高裁判所を舞台に法廷ミステリーを展開するのもよかろうが最終クールにはインパクトがなさ過ぎる。「死ぬな!テツ」とかいうサブタイトルでデカブレイクが殉職したら、戦隊物始まって以来の2年目突入(「太陽にほえろ!」)も夢ではあるまい。とにかく刑事物の末端に籍を置くのだから、清く正しいデカ魂を子供たちに教えるようなドラマとして「デカレン」世界を完成させて欲しい。「この世にやまない雨はない。」「正義を信じるものが勝つのよ。」こういう言葉はテストに出してもいいのだ。小学生は心に刻まなくてはならない。
注・1……この文章は「デカレンジャー・スワットモード」の登場以前に書かれたものです。