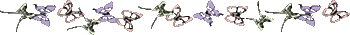
 哀憑歌 NU-MERI(2008年、サテライト、GPミュージアムソフト)
哀憑歌 NU-MERI(2008年、サテライト、GPミュージアムソフト)
木下あゆ美が「普通の」女子大生を主役で演じる映画。一年前に完成していたものの、お蔵入りしてしまった様子である。話のスケール感から言えば、ホラーVシネ的作品である。アニマル・パニック・ホラーというふれこみなのだが、魚河岸の魚の臓物や深海魚のホルマリン漬けが見た目にグロテスクだったくらいで、恐怖を求めるホラーファンは肩すかしを食らったように感じるだろう。不気味な予兆があって、惨殺死体が発見され、得体の知れない何かがヒロインの周囲の人たちを襲い、ヒロインに迫る。ヒロインが悲鳴を上げて、逃げまくるクライマックス。確かにこういう構造はあるのだが、この平板さは何だろう。前半のゆっくりとしたテンポに伏線や禍々しさが感じられないので、段階的に盛り上がっていかないのだ。監督のセンスに問題があると思われる。それを象徴するカットは風呂場で溺れかけている友人を木下あゆ美が救うシーン直後のつなぎだ。次のシーンで友人は水死体として海に浮かんでいるのであるが、救うシーンは友人の顔のフェードアウト、水死体となった友人の顔のカットインで繋がっている。しかし、あの場合はヒロインである木下あゆ美のフェードアウトで終わらせるべきである。それでなくては主人公足りえない。その場の雰囲気で編集してはならない。編集の責任と言うよりも監督の責任であると言える。ドラマの主軸をどこに置くかという信念が足りないのではなかろうか。
話は魚の怨念と言うよりもバイオテクノロジーが海産物のゾンビを生み出したという科学的な内容で、和風ホラーにありがちな怨念とか言う陰湿なものが感じられない。アメリカンなゾンビファイトものといってもよい。それ自体は悪くないはないのだが、精神的に迫ってくるものがなく、襲ってくる海産物ゾンビが無意識に単発的な攻撃をするだけなので、恐怖感や絶望感が盛り上がらないのである。殺人魚フライングキラーを誰でも想像したと思われる「鯛のお頭アタック」は本家のそれと同じような衝撃であって、つまり失笑を禁じ得ない。第一、鯛のお頭がゾンビになろうと、トビウオでもあるまいし、空を飛ぶのは説得力がなさ過ぎる。「触手系昆布の攻撃」もありがちだし、面白かったのは「噛みつくアワビ」だったが、攻撃が淡泊すぎた。血まみれの木下あゆ美はスクリームヒロインよろしく、あっという間に傷口を再生してしまうは、助けに来たはずの虎牙光揮を逆に助けてしまうはというタフネスぶりを発揮する。マッドサイエンティストたちの野望も死因も不鮮明だし、ファーストシーンで風呂場で死ぬ女性の死因も不明。木下あゆ美の友人の悪夢や死因も不可解なまま。その死体に生えていた鱗にいたっては夏木陽子が1980年に主演したテレビドラマ「恐怖の人喰い鱶 鱶女」と大して変わらんペインティング。とかく脚本や演出に整合性がない。
刑事と警部の演技にはリアリティがなく、かなり問題がある。学生映画的なノリが感じられて、印象を弱くしている。峰岸徹が出てくれたのなら、せめて彼に警部役をやってもらえていれば、印象はだいぶ変わったろう。魚河岸の人たちも女子大生たちもリアルに描かれていたのに、事件にリアリティを持たせる立場の警察があれではまずい。

肝心の木下あゆ美だが、これはもう言うことなし。絶品である。やっと「普通の女性」を演じる彼女を堪能できた。「マスサン」もどちらかというと「普通の女性」だったのだが、あちらは如何せん漫画的だった。こちらは22歳の普通の女子大生を嬉々として演じているといった印象が強い。「元気な魚河岸の娘、研究熱心な女子大生」を素直に演じているといってもいい。主人公「飯田マリ」という女性は特に個性的な癖のある人物というわけではない。悪く言うとこういう映画のヒロインになる資格に乏しいキャラクターである。先ずは設定ありきの人物を演じる場合、そこに女優としての存在感を持たせることは案外難しい。海産物ゾンビに襲われる設定として用意された「元気な魚河岸の娘、研究熱心な女子大生」は、多分誰が演じても同様な人物になるだろう。そこに木下あゆ美らしさを盛り込めるかは彼女の努力や事務所の方針といったところか。
主人公「飯田マリ」はニュートラルな女性であって、木下あゆ美そのものが持っている女優としてのパーソナリティも実はニュートラルなのだ。彼女は今まで個性的過ぎる役を引き受け続けていた。今後はこの「普通」の路線の役を多く演じて、自分らしさを磨いて欲しい。設定に頼ってばかりでは個性は育たない。とはいえ鉄火肌の江戸弁で出刃包丁を振り回し、海産物ゾンビをなぎ払うシーンも見てみたかった。そうでなくては魚河岸の威勢のいい娘を主役としたことの意味がなかったような気がするからである。
