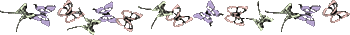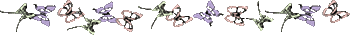
 真木栗ノ穴(2008年、株式会社ネオ、株式会社ライツマネジメント)
真木栗ノ穴(2008年、株式会社ネオ、株式会社ライツマネジメント)
昭和レトロのアパートを舞台にした怪異譚である。幻想的な文芸もどきなのかと思っていたら、実は純粋な怪談話である。都築道夫の標榜していた怪談に近い。
キャスティング的に乖離していたのは主役の西島だけだった。他は完璧、文句の付け所がない。西島の演技に申し分はないのだが、西島はイケメン過ぎてドラマから遊離している。こんなにむさい作家像にしては二枚目過ぎてあわないのだ。客を呼べる俳優をキャスティングしなければ仕方がないのだろうが、テーマ的にはいかがなものかという、商業映画の限界を感じさせる。この映画のテーマとしてふさわしいハンサムではない俳優を選ぶか、興行成績を望めるスター俳優をキャスティングすべきか。「スターが映画を作るのではなく、映画がスターを作る」というのは私が好きな言葉であるが、現実的には理想論かも知れない。好きな俳優が出ていなければ、その映画の企画そのものが注目されない限り、映画を見ようなんて気は起こりようがない。だからこそ商業映画は俳優の確保にギャラを計上する。映画にとって大切な要素はなんなのだろう。俳優?演出?脚本?リメイクばやりの昨今、商業映画の本質とは何なのか、悩んでみたいところではある。
私がこの映画で不満だったのは照明だ。日本の映像作品で一番蔑ろにされている照明だ。ビデオ全盛の世の中で、問題は「人間の目」の感覚だ。こんな状況で、こんな風に見えるわけがないのに、ただフラットな照明をたいたり、不自然な光を強調したりする。それが演出としての意図的なものならばよしとして、照明の間違いが日常の平易なシーンによく見受けられるのは噴飯物である。映像は光と影で作るものだから、照明が大切なことは言うまでもない。撮影が花形スタッフであることは承知の上だが、それでも一番大切なのは照明なのだ。光なくして映像作品は成り立たない。今後映像製作に関わりたいと思う人は心して欲しい。大切なのは照明なのだと。照明と撮影のスタッフさえしっかりしていれば、監督や役者なんていらないくらいなのだ。照明は立派な演出なのである。必殺シリーズのような外連味ばかりが照明効果ではない。SFXとは呼ばれないが、SFXとは照明に尽きるのである。

木下あゆ美は本作では「普通」の役をきちんと演じている。ただしヒロインよりも美人で魅力的に撮られてしまうのはよくない。美人に撮られるからには、映画としての効果や理由付けが必要なのだ。そうでもないのに美人に撮られてしまうと、観客の予測をあらぬ方向に持って行ってしまいかねない。本作では映画的なバランスを崩してしまいそうな勢いを感じた。とはいえ、彼女の出演した劇映画の中では、女優としての精進が十分に感じられた作品だった。テレビドラマの「ミラクルボイス」でも助演で光っていたが、本作品は更に光っている。この映画を鑑賞した人に強い印象を残したことだろう。安定した仕事を続けて演技力を更に磨いて、「小股の切れ上がったいい女」優であり続けて欲しい。
さて映画自体の出来映えは照明やスモーク描写に難があるものの、話としては面白い。謎の解明が駆け足だったり、憔悴していく西島のメイキャップが舞台のそれみたいだとか、ケチをつけるべき点は残るものの上質なホラー作品だ。グロテスクな描写はないが、十分怖い。狂気に引きずり込まれていく西島の演技も破綻が無く、総じて役者の芝居はみな合格点。木下あゆ美でさえ生硬な演技がキャストに填っていて、安心できる。彼女の出演した映画の中では間違いなくお勧めの一本。ハリウッドでリメイクされるんじゃないかな。